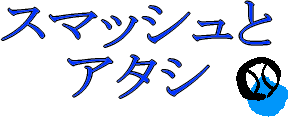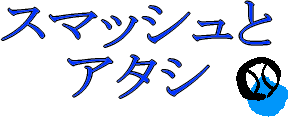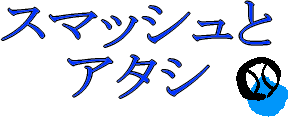
秋月ねづ
改札を抜けると、駅前の店はほとんど閉まって商店街は暗く見えた。そのはずだ、いつもよりも遅いんだから。あたしは駅の時計を見上げた。午後九時半。遅くなってしまった。ちょっと食事をするつもりがお酒を飲んでしまったから。同期の女の子達と盛り上がって、帰るに帰れなかったのだ。みんな入社して三ヶ月経って会社の事も少しづつ分かってくるにつれ、不満も出てきたみたいだった。仕事の疲れ、嫌いな上司、変な決まり、そういう色々なことだ。話が長くなって、イイ男とか、恋愛の話とかになってきた頃にあたしはやっと抜けてきた。飲み会はまだまだ続きそうだったし、それに会社の有能な男に気に入られるとか、玉の輿とか、そういう夢みたいな少女チックな話はあたし全然好きじゃない。
それより何よりあたしは早く帰らなきゃいけないのだ。多分あいつは待ってるから。
あいつとは高校時代に付き合い出した。あいつはテニスでインターハイとか上位でかなり将来を期待されてたけど、高二の時に酷い怪我をして、普通の人になった。高校を出てあたしは就職したけど、あいつは就職できなかった。あいつは行き着いたところダメ人間だった。人より高いところにいたせいで低いところまで落ちてしまったっていう感じだ。
あたしは駅から近いだけが取り柄のボロアパートを見上げた。部屋の明かりは点いていない。窓は開いているみたいだから、あいつは居るのだろう。もっともあいつが部屋を開けることなんて殆ど無い。行くところもないし、何処かへ行きたいっていう欲求もないのだ。あたしはボロアパート同士が暖をとるみたいに窮屈に隣接する細い路地を抜けて、アパートの錆びた金属の階段を軋ませて登った。
あいつは卒業と同時に実家を出た。あいつの親は優秀な子供の親にありがちな期待過剰の傲慢な親だった。あいつの親はあいつがテニスの世界で能力があったのと同じように、それ以外の世界でも優れていると信じ込んでいたし、実際それを要求した。多分それがあいつを駄目にしたんだと思う。あいつは傷だらけになって家を飛び出して、何の先行きなく、この六畳一間のボロアパートに住み着いたのだ。
ドアを開けると、あいつは窓の傍、射し込む街灯に照らされて座ってた。片手にはウイスキーの入ったコップを持って立て膝で。
「電気ぐらい点ければ?」
あたしはそう言って蛍光燈の紐を引く。明かりはいきなり六畳の部屋を隅々まで照らして、あいつは眩しそうに酒で充血した目をあたしに向けた。
「あっ、帰ってきた」
あいつは抑揚の無い声で言うと、ため息のように鼻から息を吐き出して俯く。あたしは窓のカーテンを引いて、紺のスーツを脱いだ。ハンガーにスカートがシワにならないように注意してかけて、ストッキングを脱ぐ。
「いつから飲んでんの?」
そう聞いても返事はない。あたしはため息を吐いて、ストッキングとブラを部屋の隅の籠に放り投げて、脱ぎ捨ててあったスウエットを頭から被った。
「あんたホント、どうしょもない男だわ」
あたしはあいつの向かい側に座って、ちゃぶ台のバーボンの瓶を蛍光燈に透かして見た。あいつは顔を上げて「メシ食ったの?」と訊く。あたしが肯くとあいつは微笑んだ。あたしは手を伸ばしてマグカップを取ってバーボンを注いだ。口をつけてちょっと飲むと、熱い液が喉から胃へと食道を伝っていく。
「帰って来ないと思った」
あいつは言う。あたしは立ち上がってスーツの内ポケットをまさぐって、煙草とライターを出した。
「なんで?」
あたしが煙草を咥えて言うと、あいつは首を振った。
「なんとなく。おまえがもう二度とここに帰って来ないと思った」
「へえ」
あたしは鼻で笑った。
「おれ、いつも思うんだ、夕方になると。おまえが帰って来ないんじゃないかって。外が段々暗くなって、どっからか肉とか焼く匂いしてくるとね。お前は猫みたく、もっとオイシイもんくれるとこへ行って帰って来ないんじゃないかって」
あたしは煙を吹き出した。
「馬鹿じゃないの、あんた」
あいつは静かに首を振る。
「ホントだよ。今朝、お前を駅まで送ってったろ?」
あたしは肯いた。あいつは中空を見つめながら話す。
「お前は駅まで行ったら、行ってくるって言っておれの傍を離れた。離れていくお前見てたら、おれはお前がお前じゃなくて他の……、なんて言うか、おれの全然知らない通勤途中のスーツ姿の女みたく見えて、おれはぼーっとその女の後ろ姿を眺めてた。女の手が鞄から出したケースの薄いプラスティックの定期券を抜き取って、自動改札にゆっくりと渡す。そっけなく受け取る。何ともないことなんだけど、正直魅力的だった。なんて言うのかな、優雅なんだな。お前、階段の手前で振り返って手を振ったろ? それで『ああ、お前だったんだ』って思ったんだ。
その後、お前が階段の上に消えて見えなくなった時、何となくお前はもう帰って来ないんじゃないかって思った」
「なんで?」
あたしは訊ねた。
「わかんないけど、たぶんキレイだなって思っちゃったんだな。他の奴はきっと、お前を見てこんなふうに思うんだなって……」
あいつはコップを持ったままカーテンの引かれた窓を指差す。
「お前が欲しいって思ったら、こんな隣のアパートの壁しか見えない窓の代わりに、キレイな夜景の見える窓だって手に入れられる。そうだろう? こんなおれの傍にいることなんてないんだ」
そう言いながらあいつは自分の膝をゆっくりとさすった。
「そういうこと」
あたしはため息をついた。あいつはテニスの事を考えてるんだ。
「いつまでもそんなこと言ってたってしょうがないじゃない。確かに凄かったよ、あの頃のあんた。あんたのスマッシュ。速いあんたのサーブを打ちかえそうって相手がボールに集中して、あんたから目離すと、あんたはいつのまにかネットの前にいて、馬鹿にするみたいに優しいボレー、相手のコートに入れた。そおっと届かない所に。もし相手がドタバタとみっともなくロブ打ち上げても、あんたは空に祈るみたいに左手高く上げて、ゆっくり落ちてくるボールを相手のコートに思い切り叩き込んだ。あんたはあそこを支配してた。でも、もうあんたは終わっちゃった。もうあそこには戻れない」
あいつはゆっくりとウイスキーを飲んだ。
「そうだな」
あいつは言う。
「おれはもう一生あのスマッシュが打てない。これは決まったことなんだ。おれはもうあのスマッシュまで持っていくことが出来ない。おれの膝はもうあの頃みたいに早くおれをネットまで運んでくれない。サーブを打っても相手のレシーブを、反対側に飛んでいくボールを見送ることしか出来ない。誰よりも早くネットまで詰めなきゃ、キレイなボレーを落とさなきゃ相手はあれを打たせてくれないんだ。あれが打てなくなっておれは駄目になった。テニスをやりたいとは思わない。ただ、あれが忘れられないだけなんだ」
あいつはウイスキーを継ぎ足す。
「高校を出て、テニスも諦めた。お前みたく、紺のスーツを着て就職活動もしただろう? でも、駄目なんだ。面接とかして、偉いオヤジたちの前で自分のことを話そうとすると、右手の中に甘い感覚がする。ラケットの一番真ん中でスマッシュを決めた時の抜けるような快感だよ。おれは最初、なんだろうって思った。右手がくすぐったく痺れるんだ。おれは惚けてしばらく自分の右手を眺めた。誰かがおれに大きな声でなんか言ってるんだけど、全然気にならない。なんだろうこれ? なんだろう? って。でもそのうちスマッシュの感覚だって分かったんだ」
あいつは私を見る。充血した黄色い目だ。
「その時からだよ。本を読んでても、料理の途中でも右手が甘く痺れる。そうなると何もかもが下らなく思える。膝が重たくなる。肺の辺りもズシッと重たくなるんだ。そうなるとホントに駄目なんだ」
あたしは煙草を引き抜いて咥えた。
「あんたホントにしょうがないね。きっとあんたはテニスがしたいんだよ。あんたはテニスなしの自分が嫌なんだ」そう言って火をつける。
「そうかもな。でもお前だっておれをいつか嫌いになるよ。お前が好きになったおれは、今のおれじゃないんだから」
あいつはそういって酒をあおって、あたしはため息をついた。
「ねえ、覚えてる? あんたがサービスの練習をしてるのをあたし、コートの傍のベンチで見てたこと。あんたはカネのバケツの中にいっぱい黄色いボールを詰め込んで誰もいないコートにサーブを打ち込んでるの。あんたがボールを引っぱたくたびにスパーンって抜けるような大きな音がしてボールが飛んでった。あんたは一球打つたびに首を振ったり、肯いたりして、いつまでも打ってた。バケツが空になると腰をかがめて一つ一つボールを拾った。それ繰り返して、眩しい日差しがだんだんオレンジ色になってもまだ打ってた。暗くなるとあんたはコートから出てきてあたしを見つけて、驚いて『いつから居た?』って訊いたの」
あたしはあいつの膝に手を置いた。
「あたし思ったわ。『こいつ馬鹿なんじゃないか?』 って」
あいつは吹き出して笑った。
「なんだよそりゃ、ひでえな」
あたしはあいつの隣に座り直して肩をつけた。
「ねえ。あんたは勘違いしてるけど、正直、あたしはテニスなんかやらないあんたの方が好き。あんたがテニスにのめり込んでるなんて、ちっとも面白くないもの。あんたがあたしの帰ってくるのを待ってる、あたしがあんたを捨てるんじゃないかって不安に思ってる。
そういうのってステキ。
ねえ、想像してよ。他の男があたしの事をキレイだって誉めるとこ。あんたより良い男で、ちゃんと仕事もしてて、お金もいっぱい持ってる奴があたしの事キレイだっていうの。今日から俺と一緒に暮らそうっていうの。あたしはそいつについていって、帰って来ない。今日みたく暗くなってもいつまでも。ねえ、想像してよ」
「想像してたよ。さっきまでずっと」
あいつはつまらなそうに吐き捨てた。
「もう一回だけ。お願い」
あたしはあいつの足にまたがって正面からあいつを見た。
「いい男がいる」
あたしは人差し指を立てて見せる。
「めんどくさい」
「いいから。いい男がいる」
「いい男がいる」
あいつはため息交じりに繰り返した。
「とってもいい男だよ。映画の中の誰かみたく」
「分かったよ。とってもいい男がいる」
「ちゃんと想像して! そいつが言うの。
君はキレイだ。今日から僕と一緒に暮らそう」
「君はキレイだ。今日から僕と一緒に暮らそう」
そう言った瞬間あいつの顔が少しだけ嫉妬に歪むのを見て、あたしは堪らなくなってあいつに抱きついた。
そして、大声で『あたしはあんたの傍を絶対離れない』
って叫びたかったけど我慢して、その代わりにあいつの頬っぺたに優しくキスしてあげた。ささやかなご褒美を。
叫ぶのを我慢したのは、あたしはあの表情をもっともっと見たいし、あいつがいつもあたしのことを心配してるなら、きっとテニスの事なんて忘れちゃうに違いないって思うから。そう。あいつの右手に残るくそったれたスマッシュの感触の代わりに、あいつは暗くなった部屋であたしのキスの甘い痺れを頬っぺたに思い出す。そうなったらどんなにいいだろう。
「あたし、明日は帰って来ないかもね」
あたしは意地悪く言って、あいつの首に手を回しながら笑った。
「止めてくれよ。そういうの」
あいつはそう言って顔を歪ませた。
あたしはホントにこのままでいいと思った。あいつがいつでも家にいてくれる。料理を作ってくれて、あたしを愛していてくれる。あたしの給料だけだって、ここでなら暮らしていけないことはない。でもそれはあたしだけの都合だ。あいつは日に日に駄目になっていく。あいつの人生の唯一の道は塞がれて、もうどこにも行くことが出来なくなってる。アルコールに浸って、昔見た輝かしい夢を思い出して毎日絶望してるだけだ。でも、あたしにはどうしてやることも出来ない。あいつはあいつ自身で這い出てこないといけない。あたしに出来ることといえば、せめてあいつがこれ以上落ちていかないように見張ってることくらいだった。
はっきり言って、あたしは途方に暮れていた。何処を見回しても光は見えないように思えた。でも出口はあった。後で振り返ってみるとそれはあたしにとって、思いもよらないほど単純で皮肉な、これ以上ないほど平穏で幸せな解決だった。だってあいつを穴から引き上げたのは、他ならぬ、あいつをこの深い穴に突き落としたのと同じ『テニス』だったから。
その日、帰ってみるとあいつは口笛を吹きながらスパゲティーを茹でていた。鶏のキッチンタイマーのゼンマイが戻る音と水の沸騰する音。あたしは部屋の隅にカバンを投げたとき、見慣れないバックが置いてあるのを見つけた。
「なにこれ」
あたしはバックのファスナーを開けた。中に入っていたのは、真新しいテニスラケットとウエアーだった。
「へへへ」
あいつは照れくさそうに笑った。
「だってあんた……」
あたしがラケットを持ったまま絶句すると、あいつはあたしの手からラケットを取って、手の中で二、三度回してグリップを確かめた。そして、バックの中に入っていた、ルコック・スポルティフのウエアーを羽織って、背中をあたしに見せた。『NAKAYA TENNIS SCHOOL』
「ナカヤ テニススクール?」
「そう。新しい仕事。テニス部の先輩が紹介してくれたんだ」
「ふーん」
あたしはスーツの胸ポケットから出した煙草を口に咥えた。
「まあ、がんばんなさいよ」
あたしは嬉々とするあいつの顔を胡散臭そうに眺めて、煙草に火をつけた。 あいつのそんな笑顔を久しぶりに見た。また高校時代みたいな快活なあいつに戻れるかもしれない。でも、あたしはあいつがまたテニスに関わるのは心配だった。あいつはまたテニスに傷付けられるかもしれない。あたしには素直に喜べないところがあった。
「また、あんたテニスばっかりで、あたしを放っとくんじゃないでしょうね?」
あたしはあいつの頬っぺたの肉を引っ張って言った。
「そんなことないよ」
あいつはそう言って自分の頬を撫でた。
「それよりなあ、見ろよ」
あいつは右手に持った赤いラケットをあたしの目の前に見せた。
「これ、プリンスの新作だぜ。タダで貸してくれんだって」
そう言って、あいつは鼻をつけて新しいガットの匂いを嗅いだ。あたしは鼻を鳴らした。
「ほら、もうそんなじゃないの」
「ゴメン」
あいつはそういって、左手をあたしの背中に回した。そして耳元に口をつける。
「おれの赤いラケットのこと覚えてるか?」
あたしは肯いた。忘れるわけが無い。
まだ高校時代の話だ。
実家近くの林の中であいつはスコップを持って、右足の包帯を泥だらけにして深い穴を掘っていた。あたしはクヌギの木に寄りかかって煙草を吸う、右手にあいつのラケットを握って。そのラケットはあいつがテニス用品を洗いざらいゴミに出した後に残った最後の一本だった。
「もういいんじゃない?」
あたしはラケットを左手に持ち替えて、煙草を口から離す。あいつはため息を吐いてスコップを土に突き立てた。
「そうだな」
そう言いながらも、あいつは迷ってるみたいだった。深く深く埋めないと自分で掘りかえしそうな気がするんだろう。あたしはラケットをあいつに投げ渡した。あいつは受け取って、握りを確かめる。
「おれ、四本ラケット持ってたんだけど、全部捨てたんだ」
あたしは肯いた。
「こいつだけは、どうしても捨てられなかった。別に、高価だからとかじゃない。平凡なラケットだよ。もっと高いのも、テストモデルみたいな珍しいやつもあった」
あいつは試合中にやるみたいにラケットのフレームを額に当てる。
「こいつは、いつも俺を助けてくれた。大事な時、不利な局面でもこいつの赤いフレームを見ると落ち着いた。『別にたいしたことじゃないさ』そう思えたんだ。だから負けてる時は必ずこのラケットに持ち替えた。こいつのお陰でいくつも勝たしてもらったような気がするよ」
「じゃあ、捨てなきゃいいんじゃない?」
あたしは言った。
「神棚でも作って飾りなよ」
それを聞いてあいつは少し笑った。
「分かってるよ。こいつだけ残しといてもしょうがないって。でもこいつはおれとテニスとを繋いでる最後の糸みたいな気がするんだ。なんて言うのかな。それはたぶん、おれが十年間かけて一生懸命積んできたテニスとの信頼関係なんだと思う」
あたしは首を捻った。そんなことあたしに分かるはずも無い。あいつは穴の中に座り込んだ。
「このまま、こいつと一緒に埋まりたい気がする」
あいつはそう言う。
あたしはスコップを持ってあいつの上に土をかけた。しばらくあいつは俯いて、降ってくる土を被っていた。
「わかったよ」
膝が埋まる頃、あいつはそう言って立ち上がった。そして、ラケットを置き去りにして穴を登った。そして、あたしからスコップを取って、勢いよく穴を埋め始めた。
「テニスを辞めたら勉強だ。おれ、モノ覚えるの苦手じゃないんだぜ。テニスのセオリー、トレーニングとか食べ物のこととかも専門家が読むような本を何冊も読んで覚えた。いまでも覚えてるよ。きっと、国語とか英語とか数学だって平気だと思う」
あいつは枯れ葉の混じった土でどんどん埋める。
「そしたら、新しい夢も見られると思うよ。ウインブルドンの代わりになるような楽しい夢をね」あたしはあいつの顔を見て驚いた。あいつは泣いていた。声の調子が全然変わらなかったから分からなかったのだ。あいつは目に涙を溜めて、それは瞬きのたびに零れた。
あたしがあいつの涙を見たのはそれが最初で最後だ。いまでもあいつの赤いラケットは高台の林に埋まってる。そして結局あいつは、数学や英語は覚えられなかった。好きでもないことを覚えられるほど器用な男ではないのだ。
「あの時はもうテニスなんてやらないだろうって思った」
あいつは新しいラケットをまぶしそうに眺めた。
「あの埋めたラケットとみたいな関係は、こいつとはもう作れない。プレイヤーとしてのおれはあの林に埋まっちゃったからな」
あいつはそう言ってあたしを見る。あたしはどんな顔をしていいか分からなかった。あいつは微笑む。
「でも、おれ嬉しいんだ。テニスがもう一度、おれを必要としてくれたみたいな気がしてさ。あの頃には考えもしなかったカタチだけど、とにかくテニスに関わっていられる」
「ふーん」
あたしは気の無い返事をした。鶏のキッチンタイマーが鳴き声をあげる。あたしは立ち上がって、ガスを止めた。スパゲティをざるにあげて、あいつを見ると、あいつは大事そうにラケットをバッグに仕舞っていた。
次の日からあいつはコーチの仕事をはじめた。早く起きてあたしのために朝ご飯を作って、あたしを仕事に送り出してからあいつ自身の支度をする。夕方はあたしよりも早く帰ってくる。買い物を済ませて、夕ご飯を進んで作った。あいつは少しずつ明るくなって、活動的になったみたいだ。
「今日は何してたのよ」
夕飯の時にあたしはそう聞いた。
「仕事に行った」
あいつはそう言って、里芋を口に入れた。あいつは仕事の内容をちっとも話そうとしなかったから、あたしには何も分からなかった。
「ちゃんと教えてよ。ねえ、どんな人に教えてるの?」
あいつは笑う。
「気になる?」
「別に」
あたしは缶ビールを飲んだ。
「じゃあ、いいじゃない」
あいつはそう言って、あたしが置いたビールを取って飲んだ。あたしは鼻を鳴らして、ポテトサラダを食べた。あいつは何も言わず、飲み干したビールの缶をごみ箱に投げた。
「教えてよ」
あたしは低い声でもう一度言う。あいつは楽しくてしょうがないという風に微笑んだ。
「分かったよ」
あいつは言って、大きく息を吸い込んだ。
「高校生の女の子」
あたしはゆっくりテーブルを端にどけて、あいつのムナグラを掴んで押し倒す。あたしはあいつに馬乗りになって、顔を近づけた。
「明日辞めて」
あいつは笑った。
「慌てんなよ」
あいつはそう言って起き上がった。
「最初は高校生の女の子に教えるはずだったけど、やめさせてもらったんだ」
あいつはそう言いながら、あたしの髪を撫でる。
「別にお前に怒られるからじゃないよ。その子、上手いんだ。足が速くて勘がいい。一目見て分かったよ。もっとすごく上手くなるって」
「じゃあ、教えれば良いじゃない」
あたしはあいつの手を髪の毛から引っ張り下ろす。あいつは寂しそうに笑った。
「理論的なことなら教えられる。おれより上手く教えられる奴は多分あそこにはいないよ。でも、どうしても打ち合わなきゃならない。実戦で教えなきゃいけないことの方が沢山あるんだ。あの子は上手くなるために、自分よりも強い奴とのゲームを毎日何セットもこなさなきゃならない。おれがその相手をするのは無理なんだよ」
「ふーん」
あたしはあいつの胸に顔を埋めた。
「だから辞退したんだ。残念だけどね。あんな若くて可愛い子を自分の好きな風に育てられるチャンスなんて無いよね」
あいつはそう言って、あたしにつねられて悲鳴を上げた。
「ホントは誰に教えてるの?」
あたしはあいつの目を見上げて可愛く訊いた。あたしだってその気になれば可愛い振りだってできるのだ。
あいつは目を細めた。
「想像してよ。おれがどんな人を教えてるのか」
あたしはあいつの顎に頭突きをした。
あいつは結局それを教えてくれなかった。『想像してよ』はこの間のあたしの真似をして報復してるんだ。あたしが意地悪して嫉妬させたのを根に持ってるんだ。男のくせに陰険な奴だ。きっと隠す必要のない人に教えてるくせに、わざわざ意味深に隠したりしてるに違いない、と思う。
それとも、ホントにあたしに隠さなきゃいけないような相手なのかもしれない。どんな人がスクールに通うんだろう。あいつは午前中から夜まで教えてるから……。あたしはその可能性の範囲が意外と広いことに気付いて愕然とした。若い人妻、休日のOL、暇な大学生に無職までありとあらゆる種類の若い女がテニススクールに通う可能性を持っているんだ。あいつの言った女子高生だってそうだ。あいつは実際可愛い女子高生に教えてて、それを口に出したのはあたしの裏の裏をかいたつもりなのかもしれない。
あたしは結論づけた。『あいつは浮気してる』
あたしの計画は次の土曜日に決行されることになった。あたしは会社の同僚にシックな黒のプルオーバーと同色のキャップを借り受けて、あいつに分からないように押し入れの奥に隠した。これであたしは土曜日あいつに気付かれずにあいつを見張ることが出来る。あたしはあいつがスコート姿の可愛らしい女の手首を取って、フォームチェックしてる現場を押さえることが出来るだろう。あいつは相変わらず口笛を吹きながら煮物を作ってる。今に見てろ、尻尾を掴んでやるから。
「天気が良いから洗濯頼むわ」
土曜の朝が来て、あいつはトーストとハムエッグを食べ終わるとそう言って立ち上がった。
「ああ」
あたしは肯いたが、そんなつもりは毛頭無かった。今日の予定は既に決まってる。あたしは気のなさそうに、窓から入る陽射しの中に煙草のけむりを吐く。あいつはドアを閉めて出ていって、あたしは一人になった。あたしはコーヒーを一口すすって、しばらく陽射しに漂う埃を眺めて、十分な時間が経ったところで立ち上がる。食器を流しに出して、鏡に向かい、髪を後ろで一つにまとめた。スウエットを脱いで、紺のジーンズをはく。押し入れの奥から紙袋を取り出して、借りた服を着込んでキャップを深めにかぶった。これであいつにも分からないはずだ。あたしは少年のようになった自分の姿を鏡に映して肯いた。
今日の天気は本当によかった。商店街を駅とは逆向きに歩いていく。テニスコートまではたいした距離ではない。あたしはジーンズのポケットに手を入れた。こうしていると別の人物になったみたいだ。あたしは眩しいくらいの陽射しと陰を交互に潜り抜けて坂を登る。左右に木が並びはじめてテニスボールを引っぱたく音が聞こえてきて、あたしは誰にも見られないようにそっと、テニスコートの裏へ回った。ここのテニススクールは思ったよりも大きかった。五つも六つもコートが並んでいて、奥には屋根のある練習場も見えた。日曜日の午前中だけあって、どのコートにも人がいるようだった。あたしはあいつのの姿を探しながら、コートの金網の間にある細い道を奥へと歩いた。あたしは奥から三つ目のコートであいつを見つけた。あいつは長い髪をした男と打ち合っている。あたしはあいつの相手が男だったことで少し安心した。男はまだ初心者らしく、懸命にボールを打ちかえしていた。あいつは男が打ちやすいように、殆ど同じ場所に何度もボールを送り込んでいた。あたしはそのコートが良く観察できてなおかつ、あいつから見つかりにくいところをさがして、事務所前のベンチに腰を下ろした。ふたりは殆ど口をきかずに打ち合っていた。あいつは膝をかばいながら届くボールだけを打ち返し、届かない時には新しいボールを打ち出した。あいつの手持ちのボールが無くなると、二人はネット際で少ない言葉を交わし、ボールを拾い集めて、また打った。それを何度も繰り返して、二人は選手が試合でやるみたいにネットを挟んで握手をした。それは終了の合図だった。
ちょうどその時サイレンが鳴って、あたしはお昼になったことに気付いて立ち上がった。各コートからもぞろぞろと人が出てきて、コーチ達は事務所のある建物に戻ってきた。あたしは立ち上がって家に戻った。あたしはスウエットに着替える。午前中にはあいつの浮気の証拠は掴めなかった。あいつはあの無口な長髪と打ち合っているだけだった。あたしは午後も見に行く決心をして煙草を咥えると、食パンを抱えたあいつがウエアーのままで帰って来た。
「まだ洗濯してないじゃんか」
あいつは不満そうにあたしを見る。
「後で」
あたしは精一杯気だるい振りをして言った。あいつはため息を吐く。
「乾かないよ」
あたしたちはあいつの作ったトマトとキュウリのサンドイッチを食べた。あいつは食べるとすぐコートに戻って、あたしも着替えて後を追った。
午後のあいつの相手は五人ほどの子供たちだった。子供たちは並んで、あいつの放り投げるボールを一人ずつ打っていた。あいつは午前中とは違って、陽気に子供たちの相手をしていた。子供が上手く打つとあいつは歓声を上げて、失敗すると大袈裟に慰めた。女の子の一人が上手くコーナーにボールを落とすと、あいつは口笛を吹いた。
「あれはヒンギスでも取れないな」
あいつは芝居がかった調子でそう言って、女の子ははにかんだ笑いを見せた。 あいつは一人一人に声をかけて、ボールの缶を狙わせたり、フォームを直させたりした。あたしは正直驚いていた。あいつに子供の相手ができるとは思わなかった。でも実際、あいつは優秀な保父さんみたいに子供たち全員を満足させていた。子供たちはあいつの言うことを真剣に聞いて肯いた。子供たちはあいつを尊敬しているみたいに見える。時々、子供たちを休ませる時、あいつは速いサーブで缶を狙って打ったり、曲芸みたいなことをして子供たちを楽しませた。あたしは意外なところにあいつの才能を見出した。いや、元々あいつにはテニスに関する限りあらゆる才能があった。教えることだって問題ないはずだ。テニスの好きな子供たちと、あいつは良い関係を作ることができるだろう。テニスが好きな子供たちをあいつが嫌うはずはないし、テニスの好きな子供たちがあいつのテニスの才能に憧れないはずはないのだ。
あたしはあいつと子供たちの微笑ましい関係を少しだけ羨んだ。その時あたしの中にある計画が生まれて、あたしはベンチから立ち上がって事務所のドアを押し開けた。
薄暗い事務所の中では、初老の男性が事務仕事をしていた。あたしが入っていくと、男性は目を上げた。
「こんにちは」
男はそう言って、にこやかに笑った。男は本来、外で仕事をする人間らしく幾重もの日焼けのためか浅黒い顔をしていて、白いポロシャツを上品に着こなしていた。
「こんにちは」
あたしもそう言って、男が指し示した椅子に腰を下ろした。
「レッスンを受けたいんですが」
あたしは、窓ガラスの外陽射しの中で子供たちとプレーをするあいつを指差した。
「あの人に」
それを聞いて男は鼻の下に指を当てて吹き出した。
「残念ですが、お嬢さん。彼は駄目なんですよ」
「何でですか?」
男は呼吸を整えるために深く息を吸い込んだ。
「面白い話なんですが、彼との契約に『十二歳以上、四十歳以下の女性のレッスンは受けない』という約束があるんです」
あたしもそれを聞いて吹き出してしまった。あたしたちは二人して少しの間笑った。
「でも、あたしなら平気だと思いますよ」
あたしはそういって、男は不思議な顔をしたが、すぐに気付いたようだった。
「じゃあ、あなたが彼の」
あたしは肯いた。
「はじめまして、あいつがお世話になってます」
あたしがそう言うと、男は何度も肯いた。
「はじめまして、ナカヤです」
ナカヤは右手を出して、あたしはそれを握った。
「彼から聞いてますよ。あなたは彼の恩人なんですってね」
「恩人?」
あたしはびっくりして聞き返した。ナカヤは肯いた。
「テニスが出来なくなっても、どうにかやってこれたのはあなたのお陰だって。あなたはここではこう呼ばれてるんですよ。かれの『嫉妬深い恩人』ってね」
あたしは恥ずかしくなって俯いた。なんであいつはそんなことを言うんだ?
「いや、あたしはナカヤさんに感謝してるんです。ここに来てから、あいつは別人みたいなんですよ」
あたしはそう言うと、ナカヤはにこやかに笑った。
「僕はね。じつは彼の高校時代を知ってるんですよ。僕に言わせれば、彼はその年の目玉選手だったんです。雑誌にも何度か載りましたしね。順位はまだまだだったけど、将来性が抜群でしたね。彼はどんどん上手くなるはずだったんです」
ナカヤは眉をひそめ、ため息を吐いた。
「でも、あんなことになってしまって……。彼は消えてしまって、僕も忘れかけてたんですが、彼の先輩がウチによく顔を出すんです」
ナカヤはあいつの先輩が勤めてるスポーツ用品メーカーの名前を言った。
「それで、世間話の中に彼が出てきたんです。僕は彼の出身校を覚えてましてね。それで彼がテニスから離れてるって聞いて、ぜひ連れてきて欲しいって言ったんです。」
それを聞いて、あたしはすこし心配になった。
「あいつ、役に立ってるんでしょうか? あんな足で……」
ナカヤは何度も肯いた。
「彼の理論は素晴らしいですし、何よりプレーが正確です。何の問題もありませんよ。ただ、彼のために残念なのはコーチとして優秀な選手を育てられないことですね。でも、それを抜きにしても優秀なコーチですよ。何より人望があります」
ナカヤは目を細めて窓の外のあいつと子供たちをしばらく眺めた。そして、あいつが子供たち一人一人とネット越しに握手をするのを見ると、慌てたようにいそいそとこっちを向いてあたしに悪戯っぽく笑いかけた。
「で、レッスンはいつにします?」
あいつはため息を吐いて、手に持ったボールを二度地面で弾ませた。
「どういうことだよ」
あたしは笑って、あいつにウエアーのテニススクールの文字を見せた。
「どう? 似合うでしょ」
「聞いてないよ。ただビジターのレッスンだって……」
「ビジターのレッスンでしょ」
あいつは戸惑った風に事務所前のベンチに座るナカヤに目を遣った。ナカヤは面白そうに笑ってる。
「契約違反だ」
あいつは吐き捨てるように言った。
「契約? ああ。あんたカワイイね。『十二歳以上、四十歳以下』だっけ?」あたしはあいつの頭を撫でながら笑った。あいつはあたしの手を避けた。
「畜生。うるさいよ。もうレッスンするよ。まずはグリップからね」
あたしはおかしくてしょうがなかった。
「はい、コーチ」
あたしは笑いながら言った。
そうして、あたしはあいつにテニスを習い始めた。日曜の午前中最後のレッスン。あたしはお弁当を作ってコートに向かう。レッスンが終わったら、ベンチで二人、お昼ご飯を食べる。
さしあたって、あたしの目標はスマッシュだ。いつか上手くなったら試合に出て、あいつのために最高のスマッシュを決める。速いサーブ。速い足。正確なボレー。そして完璧なスマッシュ。あたしが高校時代に見た、あいつの最高のプレー。あたしは覚えてる。あいつがどう走ってどう打ったのか。忘れるはずがない。だってあたし、ほんとは
『テニスをしてるあいつが大好きなんだから』
index/
novel/
shortstory/
fantasy/
bbs/
chat/
link