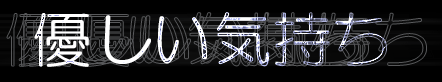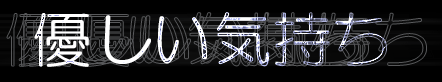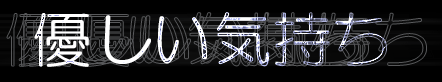
凩 優司
世紀末を越え、僕達が手にした物とは一体なんだったのだろう?
きっと誰もがそうであるように、僕も多くの物を手にしてきた。今ではもう思い出せもしない、そんなガラクタばかりを。
そして僕達は失ってきた。何かを得ようとした代償のように、本当に大事な物を少しずつ長い時間をかけて失い続けて来たんだ。
それは誇りとか信念とか呼ばれるものだったり、愛とか希望だったり……想像力だったりした。
僕には想像力と言うものが欠如している。人の痛みが分からない。いつもふとした一言で人を容易に傷つける。そしておそらく一番の問題は……それがどうしていけない事なのか分からない事なのだろう。
僕も澄乃も誰も彼もが死んでいくだろう。文化も知識も世界にある何もかもが消えていくだろう。それは確定した未来。僕達は知ってしまっている。
世界はいつか必ず滅びの時を迎えるのだと。
だから僕は今の生を実感する事ができない。僕はいつもすでに終わってしまった自分の生を追体験しているような気分で今を生きている。全ての感覚を希薄に感じたままで。世界が終わるなんて理解はできても信じる事はできない。
世界が終わろうとしている、今になっても。
黒い空から吹きつけてくる風が、何重にも着込んだ服を突き刺すように通りぬけ、僕の体温を奪っていく。寒さや痛さが僕にリアルを運ぶ。幸せや温もりなんかよりも生を感じさせる圧倒的なリアルを。
僕は手袋を隔てて金属性のバットを握ってみる。僕にとって世界はそうやっていつも何かを隔てて存在している。バットにこびりついた血を見ても、現実感が高まる事はない。核が世界に降り注ぎ、世界に終わりが告げられてから、僕は何人の命をこのバットで奪ってしまっただろう。人をバットで殴る事にも現実感はなかった。多分、僕は痛くないからだろう。返り血を浴びる時だけ、微かに現実を思い出すのが精一杯で。
狭い通りを抜け、かつてのメインストリートに出る。だけどそこに明りはない。そこにあるのは静寂と、厚く覆われた雲から微かに差しいれられる光だけ。
「そう言えば、ここらへんだったな……」
僕は思い出す。戦争が起こるずっと前。僕はこの道を通り、高校へと向かっていた。その時、僕のすぐ傍を急スピードでバイクが追いぬいていったんだった。僕は思った。『危ねぇな! あんな奴はさっさと事故って死ねば良いんだ』って。それがすぐ現実の事になるとは思いもせず。
急ブレーキの音がした。トラックの脇を追いぬこうとしたバイクが、そのサイドに接触し転倒をしたのが見えた。そしてそのまま後輪に巻き込まれるのも。一瞬にして、僕が憎悪を向けた人間は、ただの肉塊に変わり果ててしまった。
覚えているのは『ああ、人間っていうのは生き物だったんだ』という認識。そこには原型をとどめた体と、そして撒き散らすように内側の肉を露出させた頭部があった。
僕はあの時、叫ばなかった。駆け寄りもしなかった。僕はただ道端に倒れ込むと、胃の中のものが全て無くなるまで、ただ吐き続けた。映画や漫画の中にはない、死と言う物の本当の姿がそこにあると思えた。
他人の痛みに……その喪失に、あそこまで現実を感じられたのは、あの時だけだった。過去という物が懐かしむための物であるなら、あれは僕にとって過去だった。他人の死にもすっかり慣れてしまった今となっては。
下校途中に寄っていたコンビニが見えてきた。明りの消えたコンビニほど、ここがすでに廃墟なのだと思い知らせるものはない。暗がりを恐れるようにゆっくりと僕は店内に足を進める。乱雑とした棚。商品は無残にも床に落ち、踏み砕かれている。僕はできるだけそれを踏まないように押し入っていく。
誰もいないと思われるその店内から、その時……音が聞こえてきた。荒げた息、それは暗闇に閉ざされたこの世界で、微かに灯る生の証だ。
音はバックヤードから聞こえてきた。ゆっくりと近づいていく。手に力をこめて。いつだって相手の命を奪えるよう、覚悟を決めて。相手の命を無造作に奪う。その覚悟がなかったから、こんな世界になった後で出会った人々は、みんな僕に命を奪われる事になった。
そして目に映ったのは、僕の知っている顔だった。
「……よぉ」
僕の声を聞いて男が顔を上げる。男はコンビニの隅で女を犯していた。その女の顔に見覚えがない事に、僕は少し安心する。
「何だ、圭一か。お前もまだ生きていたのか」
「ああ。ちょっと缶ジュースでも漁りにきたんだけど、良いか?」
「構わねぇよ。どうせ、ここ以外にもコンビニは残っているしな」
男……友則は再び、女を犯す事に没頭し始める。僕は彼を刺激しないように、離れた在庫置き場へ行くと、そこに詰まれた缶ジュースや缶コーヒー、それに冷凍食品を鞄に詰めていく。
遠目でうかがうと、女はまるで反応を示してはいなかった。単調な前後運動、それにただギシギシと体を動かされるだけ。きっと僕が来た事にも気がついてないのだろう。僕に助けを求める素振りも見当たらない。
女は足の腱が切られていた。友則が切ったのだろう。手当てもされないそこは青黒く化膿をしていて、腐りかけているようだった。
「ッ……」
友則の動きが止まる。どうやら射精し終わったようだった。女からゆっくりと引き抜くと、僕が彼を見ているのに気づいたようだった。
「……どうした? この女はやらねぇぜ?」
「冗談はよせよ、俺はモラリストなんだぜ」
「お前がモラリスト? ……冗談としては面白いな」
友則はケラケラと笑う。
「しかしよ、この女は良い拾い物だったぜ? 顔も体にも傷を負っていなかった。見つけてすぐゲット決定だったよ」
『羨ましいだろ?』彼の瞳がそう、語り掛けてきている。別に羨ましくもなんともなかった。だけど、そんな返答をしてわざわざ雰囲気を悪くするのは愚かな事だと思った。
だから僕は言う。
「良いね」
「だろ? お前には分けてやんねぇけどな」
「だからいいって、別に。でも……最初は抵抗しただろ?」
足の腱を切った腱を言っているのだと気づいたらしく、ちょっと友則は気まずそうな表情になる。
「まあな。でも……一週間か、その程度で全く抵抗しなくなったけどよ」
「一週間か……」
僕の言葉に、友則の表情が曇る。
「なんだよ、何でそんなひどい事を続けたんだ、とか言う気か?」
「別に……」
僕は再び冷凍食品を鞄に詰めこみながら答える。
「ただ、そういうので抵抗をしなくなるのって一週間くらいなんだ、って思っただけだよ。善悪なんて別にして、データって言うのはそれだけで面白い物だって、そう思わないか?」
僕の言葉を聞いて、友則は吹き出し、大笑いを始める。
「圭一……お前、相変わらず面白い奴だな」
「俺は真面目なだけが取り柄の、つまらない男だよ」
だけど、そんな反論は友則の笑いを一層大きくするだけだった。
「そう思ってんのはきっと……お前だけだぜ」
僕は面倒くさかったので反論をしようとは考えなかった。友則は僕に近づいてくると、僕が持っているバットに目を向ける。
「モラリスト? 真面目? 聞いてあきれるぜ。なんだよ、このバット。尋常な歪み方してねぇぞ……。なぁ、なぁ、これで何人殺したんだよ?」
今までにセックスをした女の数を競い合うように、友則が聞いてくる。
「別に大した数じゃないさ……」
僕は答える。別に数を競い合う事ではないし。一番、大切な事は生き残る事。
「思っていたほど、人を殺すのは面白い事ではなかったし。俺は向こうから近づいて来ない限りは殺さないよ」
「んだよ、つまらねぇ」
「……期待に添えられなくて悪いな」
言いながら片手で鞄のジッパーを閉め、立ちあがる。
「んじゃ俺は、十分に食料や飲料ももらったし……帰るよ」
友則は俺の言葉を聞いて、興味を露わに示す。
「帰るって、どこにだよ?」
僕の後を追おうとする友則。僕は振り返るとバットを突きつける。
「ついてくるな」
「……なんだってんだよ、随分な態度じゃねぇか」
ふてくされた口調の友則に、僕は説得をする。
「悪いな。別にお前がすぐに襲いかかってくるとは思わない。そんな理由もないしな。だけど……ずっと傍にいて安心ができるかって言えば、俺はお前をそこまで信用できない。できる事ならここで別れよう。それがお互いのためだって俺は思う。だから……」
僕はゆっくりと、その後に言葉を続ける。
「右ポケットに手を突っ込むのはやめた方が良い。俺はお前を殺したいとはあまり思わないんだ」
「気づいてたのか……」
少し楽しそうに友則は答えてみせる。ダウンジャケットの右ポケットが奇妙に膨らんでいる事に、僕はずっと気づいていた。
その中には……きっと拳銃が隠れているのだろう。
「おかしいだろう? いくら知り合いだからといって、こんな世界で武器を携帯している人間の傍でセックスを続ける。……自殺行為さ。『自分は殺される前に相手を殺す事ができる』って確信していなくちゃできる事じゃない。だからこそ俺はお前にさしたる敵意がない事も分かる。お前には俺を殺す十分な機会があった」
「……お前が、そう簡単に殺されるたまだとは思わないけどな」
僕と友則は乾いた笑みを交換し合う。
「まぁ……だから、俺としては友則にここで引いて欲しいんだよ。別に殺しあわなくたって、俺達にはどうせ時間なんてもう残されてはいないのだから」
「……まあな」
友則は肩をすくめてみせる。
「行けよ。また飲み物がなくなったりしたらここに来ればいい。多分……俺達が死ぬまでに消費できる量でもないしな」
「そうさせてもらうよ」
僕は言ってバックヤードから立ち去る。友則が僕を追ってくる気配はなかった。そして僕はまた、荒れ果てた道へと歩き出す。
戻るべき場所に、帰るために。
澄乃が待つマンションに戻る途中、雪が降ってきた。
雪というよりは雹のように固まったそれは、僕の体に叩きつけてくる。痛みを堪えるために体に力をこめる。何かを堪える事というのは嫌いな事ではなかった。少なくとも、何もない事よりは。
半年前まで、僕は近くの高校に通っていた。それがもう遠い昔のように感じられる。僕は人より秀でた事も劣った事もさほどなく、音楽が好きで、だけど完成もさせられずに途中までの曲を何曲も何曲も作って楽しんでいた。そんなどこにでもいるような少年だった。
澄乃は高校という狭いコミュニティの中で、誰よりも秀でた人間だった。学力も運動能力も美貌も、そして家の裕福さも……地方の一高校の中で、ではあるが群を抜いた存在だった。誰もが彼女に一目を置いている、多少のわがままも彼女なら許される。少し傲慢なお姫様、彼女はそんな存在だった。
男子生徒の大半は彼女に振り向いてもらおうとやっきになって、そしてつれなくあしらわれていた。僕も彼女が好きだった。幾つもの愛の詩を書いて、だけどそれを届ける事もできずにいた。僕は彼女にとってどうでもいい存在だったから。僕は自分が動いて傷つく事を恐れ、そして益々彼女から遠ざかっていった。僕にできたのはただ、家で彼女の事を考えながら自慰行為にふける事だけ。
そして、そんな日々は不意に終わりを告げる。
核が世界に降り注ぐとTVはがなりたてていた。世界はもう終わりを迎えるのだと。宗教的対立が、民族的対立が、この戦争を引き起こした。そんな事をニュースキャスターは言っていた。だけど僕は馬鹿だから、それがどういう事なのかイマイチ分からなかった。
分かるのはただ、これでもう澄乃には会えなくなってしまうんだって事。
僕は走った。彼女に会いたかった。好きだって伝えたかったのかもしれない。顔が見たかっただけなのかもしれない。全てが終わるのだと言われて、僕はようやく動き出す事ができた。
彼女の家が見えた。僕は息を切らせて門を乗り越えると、庭を突っ切ろうとする。その時だった。
僕は澄乃を見つけた。だけどその姿は、僕の望んでいた姿ではなくて。
「大丈夫、大丈夫よ、この家には核シェルターがあるの。父さんと母さんは間に合わないけど……私たち二人は助かるわ」
澄乃は男と抱き合っていた。僕は知っていたんだ。彼は悠輔という名前の上級生だった。僕が知らなかったのは、彼が澄乃の恋人だったという事。
胸にどす黒い感情が浮かんで、そして消えはしない。僕は辺りを見まわし、庭の隅にスパナが置き忘れられているのに気づくと、それを手に取って……。
気がつくと、悠輔に飛びかかっていた。
僕はスパナを何度も何度も悠輔の顔面に振り下ろす。突然の強襲に悠輔は大した抵抗もできなかった。おそらく、覚悟の違いもあったのだろう。
僕は最初から、彼を殺すつもりだった。
「け、圭一君……? な、何をするのよ! やめて、やめてってば!」
澄乃がつかみかかろうとしてくる。僕は振り返ると、ためらわずにスパナを横殴りに振った。不様な声を上げ、澄乃は倒れる。
僕の下で、やがて悠輔は動かなくなった。僕は立ち上がる。座り込んだ澄乃が呟く。「どうして……どうして」見上げた瞳に僕が映って、彼女は再び激昂する。「人殺し!」飛びかかってこようとした澄乃を僕は蹴った。彼女にそんな行動を取らせている時間はもう、ないはずだから。
彼女は腹を押さえ、うめき声を上げ続ける。僕は彼女の長い髪に触れると、少し勃起しながら尋ねる。「核シェルターはどこにある?」「誰があなたなん」殴った。「どこにある?」即答がなかったので、もう一度殴った。「あ、あっちの地下に……」
僕は彼女の髪を引っ張ると、そのまま歩き出す。「じ、自分で歩けます!」無視した。彼女は泣き始める。僕は今まで知らなかった彼女の一面を知る事ができて少し嬉しかった。
核シェルターの前に来て、彼女は鍵を使い扉を開ける。地下に続く階段が見える。その時だった。彼女が不意に駆け出したのだ。そして急いで扉を閉めようとする。僕は駆け出し、その扉を思いきり蹴り飛ばした。
澄乃が跳ね飛ばされ、階段を落ちていく音が聞こえる。僕は扉を開け、中に入ると確実に鍵を閉めた。そして階段を降りる。彼女に優しく声をかける。「ほら、立って。ここにいると危ない。もっと奥へ……」彼女はもう、何も抵抗をしようとはしなかった。彼女は黙って立ちあがろうとして……。
そして膝を折った。
「うわぁ、うわぁぁっ!」
苦痛の叫びが彼女の喉から漏れ出でる。見ると足首がありえない方向に曲がっていた。爆音が響く。シェルター全体が揺れ動き、もうタイムリミットなのだと気づかされる。僕はこのシェルターが二層構造になっているのに気づいた。安全な場所に行くためには、もう一つ扉を抜ける必要がある。その扉まで彼女を抱えて走る余裕はあるだろうか? そして僕は決断する。
駆け出す僕に澄乃は叫ぶ。「待って! 死にたくない、死にたくないぃ!」それは僕だって同じ事だ。僕は階段を再び駆け下り、そして扉を閉める。
奇妙な程に大きな音で『カチャリ』と扉を閉める音が響いた気がした。
結局僕は、その扉をすぐに開ける事はなかった。爆音は鳴り響き続け、一時間ほどでやんだ。そして一日たつのを確認してから扉を開けた。僕は澄乃を放っておいて殺したい訳ではなかったから。
澄乃は這って来たのだろう。扉のすぐ前にいた。僕は彼女をつかむと、急いで扉の内側へと引っ張り込む。彼女の異変に気づいたのは、僕から少しずれた方を見て、彼女がこう言ったのを聞いてからだ。
「圭一……君?」
僕がスパナで頭を殴ったのが原因なのか、それとも核の放射能が原因なのかはわからない。ただ彼女は目が見えなくなっていた。僕は彼女に手当てをし、そして料理を作ってあげた。それからの彼女は大人しく、従順に僕の言う事を聞いてくれた。抵抗する素振りも見せなかった。シェルターの中という閉鎖的な空間で、僕に逆らう事の愚を理解したのだろう。そんな彼女は僕にとって本当に理想的で可愛い存在になった。
僕と彼女は半年をシェルターの中で過ごし、食料が切れたので外に出た。そこは凍てついた暗闇の世界と化していて。僕は彼女の手を取りながら、彼女の父が持っていたマンションを幾つか回ってみる事にした。
三つ目のマンションが全壊を免れていた。僕は彼女の『風力発電の機械が残っているはず』だという言葉を聞き、一日かけて修理をする。かろうじて直った機械は電力を供給しはじめ、暖気が部屋に届く。ようやく人間らしい生活を取り戻した気になる。
扉という扉に鍵をかけ、セキュリティに心を砕く。マンションに残された死体を全て運び出し、GSから運んできたガソリンで焼き尽くす。そうやって僕は僕が望んでいた場所を作り出した。僕と彼女が残されたわずかな時間を、二人で過ごす事のできる場所を。
そのマンションが近づいてきて、僕は足を速める。凍った路面に足を取られないように、できるだけ急いで。玄関でカードを通しセキュリティを解除すると、5階まで駆け上がる。震える手で鍵を開けると、僕は声をかけた。
「ただいま」
「……お帰りなさい」
僕の方を振り返り、澄乃が言う。喜べばいいのか、悲しめばいいのか分からない……そんな口調で。
僕は彼女に近づくと優しく肩を抱き寄せた。彼女は僕の手の内で少しだけ体を固くする。そんな時、不意にチャイムが鳴った。
「……え?」
澄乃が不安げに声を上げる。僕は彼女から手を離した。
「ちょっと……待ってて」
言って僕は隣の部屋に向かう。そこには玄関とを繋ぐインターフォンがある。僕はドアを固く閉め、声がもれないように気をつけた。
電源を落としていたディスプレイをONにする。そこに映った姿は、僕が予想していた人物だった。
「……着いて来るなと言っただろ」
受話器を上げ、僕は言う。
「へぇ〜ここ電気通ってんだ。すっげぇな。核が落ちてから初めて見たよ」
そこには飄々と笑ってみせる友則の姿があった。
「人の話を聞いてるか……?」
「聞いてるさ、だけどもうすでにアウトだろ? 俺はこの場所を知ってしまった。となると、俺がここにいようが中にいようが、圭一の危険性はさほど変わらなくなる。本気になればこんなセキュリティ、壊して入る事は難しくないんだからな。なぁ、中に入れてくれよ。仲間外れにすんなよ。あそこは寒いんだからさぁ」
僕はすっと目を瞑る。それから外に舞う雪よりも冷たい声で彼に告げた。
「帰れ。そうじゃないと後悔する事になるぞ」
受話器を置き、ディスプレイの電源を落とす。部屋を出た僕を迎えたのは、心細そうな澄乃の姿だった。
「誰か来たの?」
「いいや、ただの誤作動だよ。雪か何かがインターフォンを押し込んだんじゃないかな」
僕は言って、そのまま彼女に気づかれないようにバットを手に取る。そしてベランダへとそっと移動する。このマンションには四階部分まで壊れずに残っている非常階段があった。僕が住居を五階に決めたのは、そういう理由で。
そして息を潜めて待つと、彼はやってきた。
「……よっ、と」
友則は四階まで登ると、壊れて足場の失われた非常階段の手すりにつかまる。何度か力を入れてみて強度を確かめると、彼はゆっくりと近づいてきた。光の漏れる、僕のいる場所へと。
安定した力を込め、友則は確実に僕の方へと近づいていく。そしてあと一歩の所まで来て……僕は物陰から姿を現す。
「よ、よぉ……」
僕の姿に気づき、友則は悪戯が見つかった子供のように笑ってみせた。
僕はためらわなかった。
「後悔する事になるって、言ったはずだぜ?」
金属バットを思いきり友則の頭上に振り下ろす。しん、とした空気の中……耳を塞ぎたくなるような叫び声があがる。
「な……なんでそこまで!」
僕は答えなかった。ただ黙ってもう一度バットを振りかざす。
「チッ!」
友則が素早く右手をポケットに入れる。それで勝負は決まった。
僕はバットを再び振り下ろした。今度は友則の左手に向けて。
骨が粉々に砕ける手応えがバット越しに伝わってくる。それが最後だった。
「あ……」
苦痛に歪む友則の顔が、今度は恐怖に歪む。
彼の手は、手すりから離れてしまっていたから。
「……馬鹿、だな」
叫び声を上げて落ちていく友則。一呼吸おいてから、大きな物が地面に叩きつけられる音が響いた。
「……何があったの?」
「いや、何も」
僕は嘘をついた。ばれる事がわかりきっているのに。いくら硝子が防音だといえ、先程の音が澄乃に届いていないはずはないのに。
「だって、何か悲鳴みたいな声や、何かが落ちるような音が……」
「風の音と、雪が落ちる音だろ? 俺はただ、夜景を見てきただけさ」
「夜景? 綺麗なの?」
僕は頷く。
「ああ、綺麗さ。煌くような光がぽつぽつと灯っているんだ」
全ての光を吸い尽くすような漆黒の闇を見つめながら僕は言う。そこに命は感じられなかった。今こそ世界は死にゆくのだと、思い知らせるような景色。
「うん……見える気がします。きっと綺麗なんだろうな……」
彼女も僕が言っている事は嘘だと分かっているのだろう。でも、それでも信じたいのだろう。
この世界が、まだ終わりを告げない事を。
彼女の儚い願い。それが叶わない事を僕は知っている。僕はそっと目を閉じる。そして想像してみる。彼女のまぶたに映る、明りの煌く夜景を。
それはきっと、綺麗な夜景に違いない……そう思えて。
「どう、したの?」
僕はいつの間にか泣いてしまっていた。今ではもう失われてしまった物。それがいかにかけがえのない物だったか、感じられてしまって……。
「なんでも、ない」
言って僕は彼女を抱きしめる。彼女が息を飲む。そこに僕は拒絶の意思を感じ取る。別に構わなかった。彼女がどれだけ僕の事を憎んでいても、彼女は僕に逆らう事ができないのだから……。
澄乃の服を脱がしていく。いつものように。彼女はきっと、僕に犯されている間に、どれだけ苦痛な表情を浮かべているのか知らない。そんな力のない彼女を見て、僕がどれだけ優しく笑いかけているのかも。
僕は世界が終わりを迎えてから、一つだけ分かった事がある。僕は人より優位に立たないと、人に優しくする事ができない人間だって事。それがどれだけ歪んでいる事なのかは、なんとなくだけど分かっている。
だけどもう、誰も僕を狂っているとは言ってくれない。
ゆっくりと愛撫を続け、そっと指を刺し入れる。彼女が苦痛と快楽に引き千切れそうになっているのを、それでも僕がいないと生きてはいけない現実に耐えているのを、僕は嬉しく眺める。
「圭一は……そんなに私とするの、好き?」
彼女は精一杯、僕に笑いかける。引きつった笑いを。それに気づかないのは彼女だけ。僕は彼女への愛しさがこみ上げてくるのを抑え切れなかった。
どれだけ僕が嫌いでも、彼女は僕以外選べない。
僕は彼女を横たえると、いつものように何度も可愛がる。彼女となら、いつまでも終わらない夜を過ごせそうな気がするくらい、何度も。
そして三度目が終わった時に、ふと思った。
誰も僕を狂ってるとは言ってくれない、そんな事は……ないんじゃないかと。
目の前で彼女の胸が上下する。彼女は生きている。僕の与える生にすがって。
だけど、その生がそうまでして手に入れたいものではないと、彼女が覚悟を決めたら。
彼女は僕が狂っていると罵ってくれるだろうか?
僕は笑い出す。澄乃が弱々しく手を伸ばす。
「どうしたの……?」
「なんでもない、なんでもないんだ」
だけど僕の笑いは止まらない。彼女の手を取って、僕はそっと手の甲にキスをする。
澄乃が僕を拒絶する未来。それは来るのかもしれない。だけど、それでも。
澄乃は僕から逃れる事はできないだろう。
僕は再び、そっと手の平で乳房を撫でる。夜はまだこれから。世界は終わろうとしている。だから僕は僕自身の幸せのためだけに、彼女の温もりを手放さないようにしよう。それがどれだけ彼女を傷つけていても、僕にそれは分からないのだから。
「圭一……?」
名前を呼ぶ彼女に、僕はそっとキスをして……そして耳元で囁いた。限りない愛情を込めて。
「愛しているよ」
ひどく、優しい気持ちで。
index/
novel/
shortstory/
fantasy/
bbs/
chat/
link